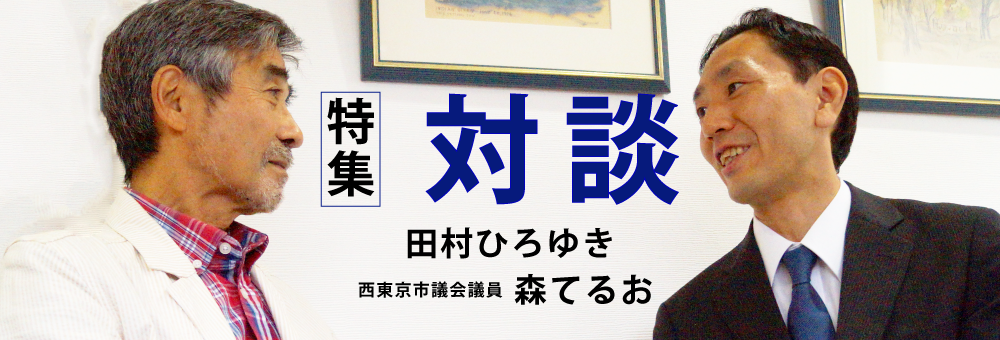10月14日、15日の2日間、企画総務委員会の視察でした。初日は岐阜県各務原市へ。ちなみに「かかみがはらし」と読みます。ただでさえ読みにくい上、駅名や高校名では表記や読み方が微妙に違うとのことで、先方の職員の方もアイスブレイクのネタとして話されていました。
視察テーマは2つあり、1つ目は新庁舎建設事業について。令和3年に高層棟が、令和5年に低層棟が完成した新庁舎は、全体的に木質系の色調で温かみのある感じ。課ごとの色分けがされ、目線の高さにも各課の名前があり、目指す窓口がわかりやすくなっています。各所に椅子や机があり、ちょっとした休憩や打ち合わせに使えるようになっていました。ロビーでのピアノコンサート、廊下を使った展示スペースもよいと思いました。




太陽光の採光装置による照明負荷の軽減など環境への配慮がされ、免震構造を採用し防災拠点の機能が発揮できるような庁舎になっています。


低層棟の市民交流スペースは、当初カフェを入れる構想だったものの、コロナ禍の影響で事業者が入らず、厨房設備も設置されなかったとのことで、その点はちょっと残念だったなと感じました。

一番驚いたのは、建設にあたって庁舎整備基金をわずか5年で80億円も積み上げたという話です。このところ毎年1億ずつを積み立てている西東京市からすると、にわかに信じがたいくらいのハイペースですが、市長がやるという強い意思があればできる、ということなんでしょうか。
市役所内には、水道水のPFAS対策に全力で取り組んでいる旨のポスターが掲示されており、こちらの取り組みも気になったところです。
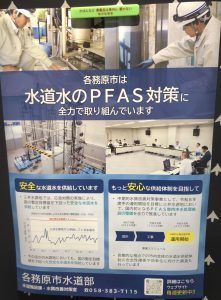
2つ目のテーマは、旧東亜町会館の活用事業について。産業会館として昭和45年に建築されたものの、老朽化し、市役所本庁舎建て替えに伴い入居団体が移転、貸館機能としても周辺に代替施設が存在したことから令和4年度末をもって廃止に。
建物を解体して用地を売却するなど、複数の案を検討した結果、近隣に市民公園や学びの森といった大きな公園がある立地を生かし、まちづくりの拠点としての活用を目指すため、建物を民間事業者に無償で貸し付け、土地使用料を得るという案が採用されました。現在では、ホールはトークイベントや音楽イベントで使用、カフェやギャラリーのテナントが入り、クラフトビールの醸造所の入居も予定されているとのことです。西東京市でも、老朽化した公共施設をどのようにしていくのかは課題です。参考にさせてもらいたいと思います。

視察2日目は岐阜県岐阜市へ。こちらも視察のテーマは2つありました。
1つ目は、第2期岐阜市シティプロモーション戦略について。西東京市も当然取り組んでいるテーマですが、今ひとつ、何を、誰に届けようとしているのかはっきりしない印象があります。岐阜市の目指すゴールは、交流人口の増加、定住人口の増加、シビックプライドの醸成の3つで、シティプロモーションの展開により、まちの活力を維持し、将来に渡り持続可能な都市経営の実現に取り組むとしています。
具体的な取組内容は多々ありましたが、若い世代をターゲットにした魅力発信冊子「エエトコタント岐阜市」は市民参加で制作し、二十歳の集いや岐阜市内、また名古屋市内の大学等で配布しているとのことでした。
また、名古屋と比べて岐阜は地価や物価が安く、同じ収入であっても、より豊かな暮らしができることを、「質の高い暮らし」というフレーズでPRしているという話があり、同様に都心から少し離れた距離にある西東京市のPRにも通じるものと感じました。
2つ目のテーマは、ぎふメディアコスモスについて。大学病院跡地に2015年にオープンした施設で、滞在型図書館と市民との協働、市民活動サポートの機能を持つ施設です。「屋根の付いた公園」と表現されています。


こちらは、実際に館内を説明を聞きながら案内してもらったのですが、「すごい」「おしゃれ」「ワクワクする」「西東京市にも作りたい!」と、参加した議員から口々に声が上がりました。子どもや若者世代に向けたスペースから、大人向けのシビックプライド醸成を狙った「おとなの夜学」というイベント実施など、すべての世代が、自分のやりたいことや居心地の良い場所を見つけられるような空間だと感じました。


西東京市で同規模のものを建設するのは厳しいとしても、少しでも近いものを実現できたらという思いになりました。
2日間の学びをしっかりと振り返り、今後の議会活動に生かしていきたいと思います。