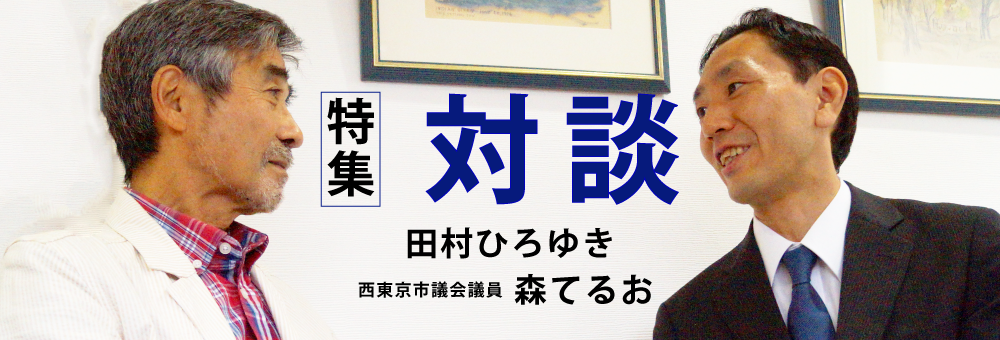10月9日、10日の2日間、「成熟社会の都市のかたち~コンパクトで持続可能なまちづくり~」をテーマに、第87回全国都市問題会議が宇都宮市で開催され、私も参加してきました。全国から1700名以上の首長や議員などが参加したそうです。
1日目の冒頭は「人口減少・成熟社会の都市とまちづくり」と題して、京都大学名誉教授の広井良典氏の基調講演でした。日本の人口は2008年をピークに減少に転じ、今後も人口減少社会が続いていく、そうした中、幸福度の問い直しがされており、ないものを探すのではなく「あるもの探し」をする時代である、高度経済成長期の東京(都市)への一極集中から、限られた地方都市への少極集中を経て、多極集中へと移っていく、といった話がありました。
これからの分散型社会の都市の姿として、ウォーカブルシティ(歩いて楽しめるまちづくり)が提起されており、これまで自動車中心に作られてきた日本の都市も、高齢化をチャンスと捉えて、歩いて楽しめるまちへと変わっていくべきという認識が示されました。また、商店街の新たな価値として、たまり場やサードプレイスとしての役割が示され、若い世代の取組が注目を集める各地の商店街の事例が紹介されました。
続いて行われたのは、「人口減少社会に対応する都市の構造改革~100年先も発展できる『ネットワーク型コンパクトシティ』の形成」と題した、開催都市である宇都宮市長の佐藤栄一氏による主報告でした。人口減少に伴い中心市街地の活力低下や地域コミュニティの衰退といった問題を抱えていた宇都宮市が、市内に都市機能を集積する複数の拠点を作り、それぞれを結んでいく「ネットワーク型コンパクトシティ(NCC)」を目指して取り組みを進めてきたことが紹介されました。
このNCC形成に向けた取組の肝となるのが、基幹公共交通である「ライトライン」の整備です。開業前には市民からも様々な意見があったようですが、開業してみると当初予測を大きく超える利用者数となり、自動車からライトラインへの転換台数が平日1日あたり約5000台、沿線の居住人口は約10%増加、沿線住民の平均歩数の増加により約16億円から18億円の医療費抑制効果を推計しているなど、様々な成果を紹介していました。これまでに視察は651件、海外からも53か国が訪れる注目ぶりだそうです。
ちなみに、今回の宿泊先のホテルがライトラインの沿線だったため、私も今回乗車体験しました。混雑等により若干遅れはありましたが、滑るような走行で乗り心地は非常によかったです。近くにキャンパスがある学生さんや、通勤の方など多くの方が利用していました。
この後は、一般報告へと移り、公共施設マネジメントに「縮充」という、縮小しても機能の充実につなげていくべきだという話、都市再生の事例として高松市の丸亀町商店街の取組についての報告、宇都宮市の事例を参考に、次世代の交通はどのようなデザインを目指すのかといった話がありました。
2日目はパネルディスカッションでした。埼玉大学大学院教授の内田奈芳美氏からは、現代における「移動」とは何か、コンパクトシティの中の「拠点」とは何かといった論点が示され、(株)みちのりホールディングス代表取締役グループCEOの吉田元氏からは、完全キャッシュレスバスの実証運行やEVバス導入の取組などの紹介が、、まちなか広場研究所主宰の山下裕子氏からは、これまでは「最速」で行ける合理性を目指してきたが、これからは「気分がいい」など移動自体を楽しむという考え方に移っていくという話が、室蘭市長の代理で登壇した市の部長の方からは、学校の統廃合や公共施設の集約の中で、100%の賛同は難しいが、住民にとってのメリットを説明して市職員が積極的に市民と関わってきた取組の話が、米子市長の伊木隆司氏からは、「まちなかと郊外が一体的に発展する都市づくり」を掲げて取り組んでいる、循環型コミュニティバスなどの話が、それぞれありました。
2日間で話された事例は、すべてそのまま西東京市にあてはまるものではありませんが、公共施設の再編や公共交通空白地域への対応などは、共通する課題です。いかに市民と対話し、前向きな価値を提示し、納得感を持って受け入れてもらうかという視点は、大切なものだと感じました。
この手の大規模な集合型研修は、一方的な講演形式にならざるを得ず、遠方の場合は移動の時間や交通費もばかにならないので、これまであまり積極的に参加してこなかったのですが、今回は関心のあるテーマだったことや、開催地が近県のため、前泊のための宿泊費が不要で交通費の負担も少ないことから参加しました。
これからも、こうして学びを深める機会を作っていきたいと思います。