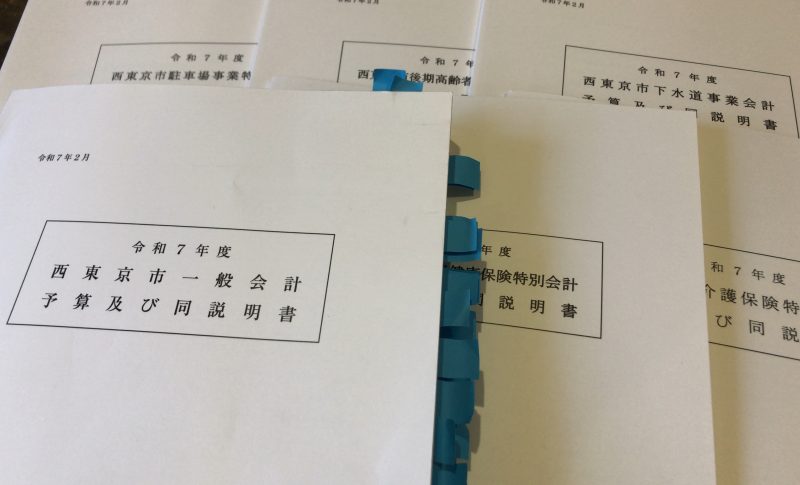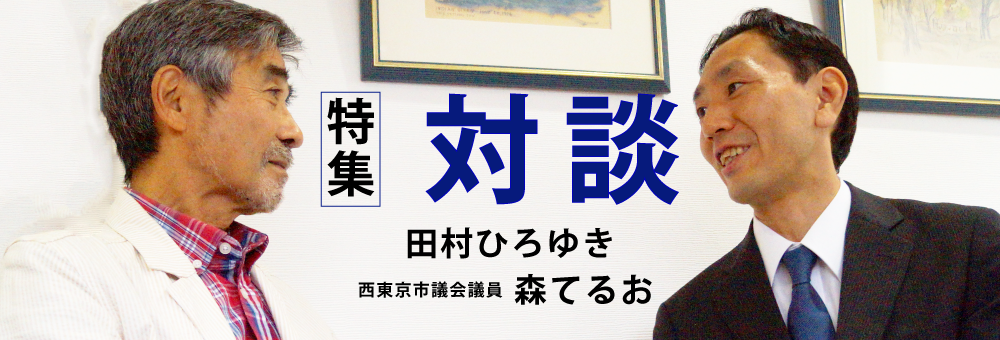3月28日、年4回の市議会定例会の中で一番長くハードな第1回定例会が終わりました。ハードな原因は新年度の予算審査を行うからなのですが、今回はその審査が異例の展開をたどり、予算特別委員会は本来の日程に3日間を追加、全体の会期日程も1日延長することになりました。
異例の展開になった大きな要因は、すでにお伝えした給食調理業務委託入札不調への対応です。調理業務委託料等を減額し、外注弁当の費用を追加する予算の訂正を行うこととなり、この対応のために予算特別委員会1日目、2日目の日程を開催することができませんでした。

本来の3日目にようやく始まった審査ですが、今度は答弁の訂正のために委員会が半日ストップしました。それは、現地建替か移転建替で検討が行われている田無三中に関し、学校の位置は教育委員会が決定するとしていたものを、市長と教育委員会が協議を行い、双方合意の上で取り組んでいく必要があるとした上で、最終的には市長が決めるという内容に変更するというものです。この件では、ある委員から「市長が決めるべきだ」という強い意見が出されたのですが、委員会の最中にわざわざ半日審査を遅らせてまで答弁が訂正されるというのは、驚くべき事態です。
予算特別委員会の混乱はこれで終わらず、最終盤の総括質疑の調整の過程で、信じられないような執行部のミスが発覚。二元代表制や議員の公平性といった点で大きな疑義を抱くような内容でした。このため、さらに丸一日委員会がストップしました。
この結果、議会事務局が最終日の本会議に向けて精力的に作業を進めてくれたものの、会期日程も1日延長を余儀なくされました。
最終日の本会議には、会期日程に影響を与えたことに加え、主に教育委員会で起きた様々な事案に関する議会への報告が著しく時期を逸していたなどの理由から、幹部職員の職務遂行に関する決議が議員提出議案として提出され、全会一致で成立しました。幹部職員には自身の職責の重さを十二分に自覚し、その職務を今一度省みること、市長・副市長・教育長には幹部職員が本来の職責を果たせる環境を整え、指導育成することを強く求める内容です。
なお、令和7年度の一般会計当初予算については、
賛成24 自民、公明、立憲、ネット、維新国民、無所属
反対3 共産
と大差で可決されましたが、多くの会派・議員が討論の中で課題を指摘しました。
私も賛成討論の中で、「多くの会派、議員が賛成の立場を表明していることに決して安堵せず、議会から多くのイエローカードが突きつけられていることを肝に銘じよ」と述べました。
賛成討論の全文は以下に掲載します(実際の議場での発言とは異なる可能性があります)。
動画は西東京市議会インターネット中継よりご覧ください。田村の討論は1時間22分5秒あたりからです。
議案第8号 令和7年度西東京市一般会計予算に対し、賛成の立場で討論いたします。
冒頭、本予算の審査においては、提出済みの議案を訂正するという異例の対応や、答弁の訂正・調整等で予算特別委員会の日程に多大な影響が出たことについて、大変遺憾であり、限られた日程の中で慎重審議を尽くそうとする議会の努力を踏みにじるものであったと厳しく指摘いたします。
予算の訂正に至った原因である、給食調理業務委託の入札不調にかかる対応においては、教育委員会から市長部局への情報共有、議会に対する情報提供の遅れがありました。自分たちでなんとかしなければならない、また、なんとかできるだろうという思い込みが、課題を共有することなく抱え込むことに繋がり、4月からの給食調理業務委託ができないという結果に至りました。市長が常日頃おっしゃっている、悪い情報こそ早く報告するという考えはなぜ徹底されなかったのでしょうか。
3月4日の私の一般質問に対し教育長は、「教育委員会は議会を通じ、市民の皆様に対する説明責任を積極的に果たしていくことが望まれております」、また「市長部局同様、適時適切な情報提供が必要と考えております。引き続き丁寧な情報提供に努めてまいります」と答弁されました。この考えは一体どこへ行ってしまったのでしょうか。かえすがえすも残念で、言葉もありません。
今回、当該の学校においては外注弁当の提供が予定されているとのことで、ひとまず安心してはいますが、温かい汁ものの提供ができないこと、アレルギー対応ができないことが課題です。また季節に合わせた献立の提供といった食育の点からも、できる限り早期に、給食調理が再開できるよう、全力を挙げて取り組むよう求めます。また、子どもたち、保護者の皆様のご不安を解消するため、丁寧な説明を尽くしていただくようお願いします。あわせて、今回の事案を教訓に、安定的な給食提供を可能とするための委託契約のあり方の見直し、給食調理室へのエアコン設置をはじめとした調理員の働く環境の改善、親子給食の見直しなどを進めていただくことを求めます。さて、訂正後の本予算は、歳入歳出をそれぞれ886億9408万3千円とするもので、社会保障関係経費の継続的な増加や、公共施設やインフラの更新により財政需要が拡大し、前年度比10.4%の増という大きな伸びとなりました。
子どもがど真ん中のまちづくりについては、子どもの医療費助成について、令和7年10月から所得制限に加えて200円の自己負担も撤廃することは、子どもたちの健康を守り、子育て世帯の支援につながるものとして評価します。また、学童クラブの過密化対策について、タイムシェアが4校拡充されることは一定評価しますが、現在予定されている柳沢小学校内への整備をはじめ、新たな施設整備についても、教育委員会と連携、調整の上進めていただくよう求めます。
次世代につなぐ環境施策については、引き続き省エネルギーや、再生可能エネルギーの利用を促進し、2030年の温室効果ガス排出量の2013年度比46%削減という目標に向けて、着実に歩みを進めることを求めます。
PFASに関連し、市議会における陳情の採択も受け、市所有の震災用井戸等の水質検査を実施することは前向きに受け止めますが、暫定基準値を上回った場合の対応について、「国や東京都及び周辺自治体の動向を注視する」というご答弁以上のお考えが出てこないことについては、本当に市民の不安の払拭という目的にかなうものであるか疑問です。周辺自治体の動向を注視、注目することは構いませんが、その上で、どのような対応ができるのかについても、あわせて考えていただくよう求めます。恒久平和の取組については、令和7年度が戦後80年の節目であることを踏まえて実施される、(仮称)戦後80周年平和大使派遣事業に期待をしています。去る2月22日に文華女子高校を会場に開催された田中熙已氏の講演会の中でも、若い世代への思いが語られていましたが、本事業が、高校生から大学生世代の若者スタッフにより企画・運営されることは、戦争の歴史と平和の大切さを次世代へ継承するという意味でも、大変意義深い取組であると評価いたします。
若者とともに進めるまちづくりについては、令和6年度から開始した若者ミーティングや、市民協働企画提案事業(U29チャレンジ部門)が引き続き実施されることに期待します。令和7年度以降、若者ミーティングからの提案を基に、具体的な取組が進んでいくものと思いますので、これまでにない新たな視点を生かした内容を楽しみにしています。中でも、若者への経済的支援については、令和6年度予算に対する附帯決議において、「次世代を担う若者・学生等の声を反映し、西東京市独自の経済的支援等を早期の実施に向けて検討すること」としておりましたので、いまだに具体的な中身が見えないことは大変残念ですが、若者のニーズをしっかりと捉えた内容になるよう求めます。
私が質疑で取り上げた中から、他の多くの議員も取り上げた、田無第三中学校の建替について申し上げます。
現地建替をするのか、移転建替をするのかについては、昨年7月以来開催されている建替協議会の中でも議論されてきましたが、学校の位置の決定について、一体だれが行うのかという点について、答弁が訂正され、学校を核としたまちづくりという考えから、公共施設の複合化も検討するため、最終的に市長が決定するとのことでした。このような重要な考え方が、なぜ事前に確認されていなかったのでしょうか。委員からの質問を受けて、予算特別委員会の最中に訂正されるというのは、驚くべき事態だったと言わざるを得ません。市長部局と教育委員会の連携という言葉は、様々な場面で常套句のように使われるフレーズですが、学校を核としたまちづくりの最初のモデルケースとして田無三中の建替が進められている今こそ、連携が求められている時期ではないでしょうか。にもかかわらず、この連携が十分にされていないのではないかと感じる場面が目立ちました。それぞれの会議体が果たすべき役割、どのタイミングで、何を議論し、相互にどう関係しているのかについて、十分に交通整理ができていないのではないかという印象を持ちました。
冒頭の給食の件も、教育委員会と市長部局がより緊密に連携し、情報共有していれば、児童生徒への影響が出ることはなかったかもしれません。何が足りなかったのかをしっかりと省みて、今後に生かしていただきたいと思います。
最後に、多くの会派・議員が賛成の立場を表明していることに決して安堵することなく、議会から多くのイエローカードを突きつけられている状況であることを肝に銘じて、今後の業務遂行にあたっていただくことをお願いして、本予算に対する賛成討論といたします。