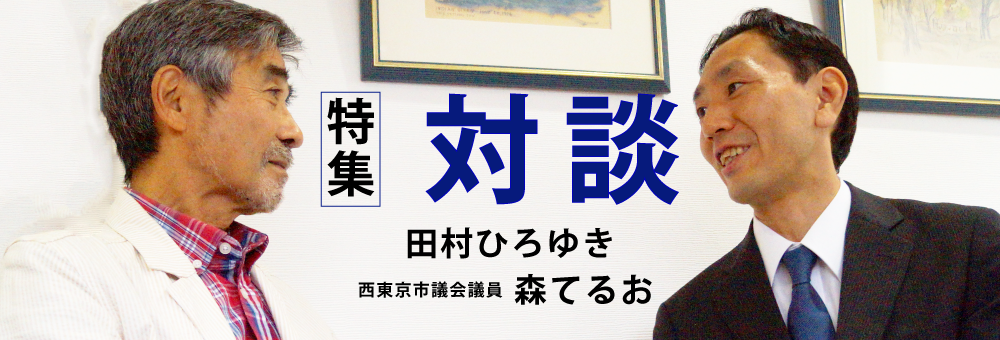7月30日、31日の両日、議会運営委員会の視察に参加し、愛知県新城市と、滋賀県大津市を訪れました。初日は新幹線の車中で津波警報のアラートが一斉に鳴り肝を冷やしましたが、幸いにして新幹線の運行に影響はなく、予定通りの日程で実施できました。また、初日の7月30日は日本国内の歴代最高気温を観測した日でもあり、とにかく暑い2日間でした。
初日の愛知県新城市は豊橋駅から飯田線で40分ほど。人口4万2千人の街です。ここでは、議会の災害対応について学びました。
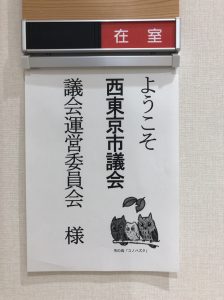
新城市議会では、東日本大震災や熊本地震を受け、業務継続計画(BCP)の必要性に対する認識が全国的に広まり、執行部側がBCPを策定したことを受け、議会でも必要なのではないかとの議論が高まり、他自治体を参考に検討を進め、平成31年に新城市議会BCPを策定しました。
その後、コロナ禍において一部議員からBCP発動を求める声が出るも、議会機能が不全となる事態ではないため、BCP発動に至らない規模の災害でも対応できる計画が必要だと、新城市議会BCPを包含する形で、新城市議会災害時対応基本計画が令和3年9月に策定されたとのことです。
ちなみに愛知県新城市と言えば、若者議会の開催で有名です。今回は違うテーマでの視察でしたが、市役所に向かう道中、若者議会からの提案でカフェ風にリニューアルしたという「まちなみ情報センター」を見学しました。若者から意見を聞くだけでなく、その提案に予算をつけて実現してしまうのが特徴です。


2日目の滋賀県大津市議会は、議会改革のトップランナーとして政策コンテスト等でも賞を受賞する常連で、多くの自治体から視察の要望があるようです。今回は、政策検討会議についてというテーマでお話を伺いました。
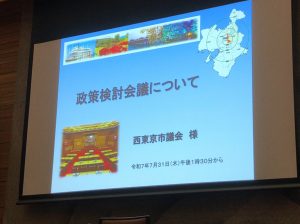
政策検討会議は、3人以上の会派(交渉会派)から条例づくり等の政策提案が行われ、複数の交渉会派の賛同が得られたものについて設置されます。提案の段階では内々に他会派にも話をしているため、これまでに提案が拒否されたケースはないとのこと。提案ができるのは3人以上の会派ですが、会議自体はすべての会派から1名ずつの参加で、1人会派であっても参加できます。仮に複数の政策検討会議が同時期に立ち上がった場合、すべての会議に参加してもよいし、参加する会議を選ぶこともできます。実際には、1人会派の議員の多くが複数の会議を掛け持ちして参加しているとのことでした。
実際にこの政策検討会議で取り上げられた内容として、
・いじめ防止条例
・議会基本条例
・歯と口腔の健康づくり
・若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくり
といった例を説明していただきました。
若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくりは、私も大いに関心のある内容です。平成27年~令和4年度という長期間にわたり、選挙管理委員会や教育委員会との意見交換、大学生、高校生、高校社会科教員との意見交換、小学校を訪問して「議員と学ぼう」と題してクイズの実施といった取組が行われてきました。
現役の高校生が出演するショートドラマ「選挙行ったよ」については、その制作過程を含めて地元テレビ局で取り上げられたとのことで、実際のドラマも含めて動画を見せていただきました。
この他、専門的知見の活用として、龍谷大学、立命館大学、同志社大学と協定を締結し、議会研修会の講師や議会報告会のファシリテーターを務めていただくといった取組についても学びました。西東京市も武蔵野大学、早稲田大学と包括協定を結んでいますので、参考になる事例だと思います。

今回の視察には西東京市議会議員28名のうち16名が参加しました。議会全体として共通認識を持てるという意味で、意義のある2日間だったのではないかと思います。