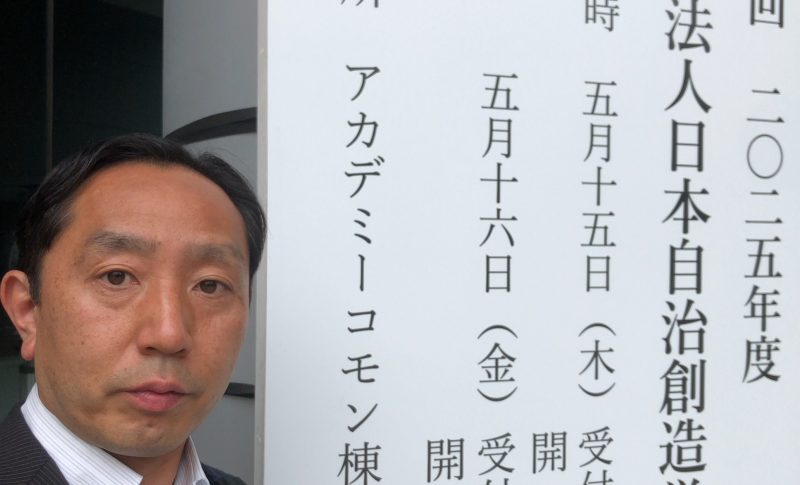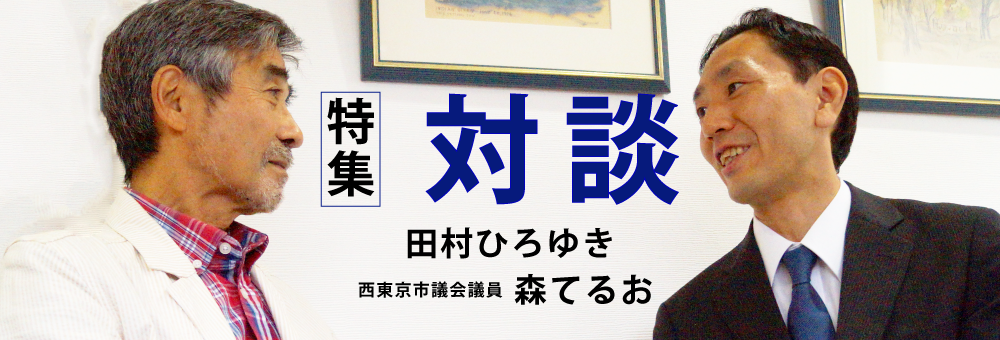5月15日、16日の2日間、お茶の水の明治大学で開催された、日本自治創造学会の研究大会に参加しました。

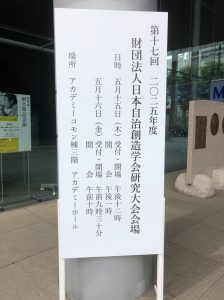
2日間で計8つの講演があり、二元代表制の問い直しや、昨年の都知事選におけるブロードリスニングの実践、能登半島地震と奥能登豪雨の報告など、多方面からの学びがありました。すべてをご紹介すると長くなりますので、印象の残った内容をいくつかご紹介します。
初日最初は「地方自治における政治の復権」と題して名古屋大学の後房雄教授が講演。戦後の自治体の変遷について、革新自治体の時代、今にも続く共産党以外の相乗り体制、改革派首長やポピュリズム首長の登場など、歴史的に振り返りました。相乗り体制では議会多数派と首長の「ねじれ」は発生しないが、選挙が無意味化する。予算提案権の欠如した二元代表制は原理的に矛盾があるという指摘でした。
自治体も議員の多数派が執行責任を担う議院内閣制を採用すべきだ、という主張には首肯し難い気持ちもありましたが、二元代表制のあり方について改めて考える機会となりました。
この他、政策研究大学院大学の飯尾潤教授は、日本の統治構造についての歴史と課題について、東京大学大学院法学政治学研究科の金井利之教授は、2024年の改正地方自治法に盛り込まれた国の「補充的指示」の内容と課題について講演。

独立行政法人国際協力機構理事長特別補佐の井倉義伸氏は、「~JICAにおける地方創生2.0・地域活性化事業への挑戦~地域との連携による様々な創生事業の実践と活用方法について」と題して講演しました。
2日目最初の講演は、AIエンジニア・起業家・SF作家の安野貴博氏。昨年の都知事選で新人・初挑戦で15万票を得たことで知られています。講演では、ブロードリスニングという手法を用いて民意を見える化し、その案をオープンソースソフトウェアの開発手法を用いてみんなで磨き、「AIあんの」と名付けたアバターがみんなに伝えるという都知事選での実践を説明。参加していた議員も興味津々という感じでした。
参院選への挑戦を表明している安野氏。ここ1年の間にも導入のハードルは低くなっているとのことで、今後の選挙の姿が変わっていくかもしれません。


続いての講演は日本大学法学部政治経済学科専任講師の安野修右氏。インターネット選挙の歴史と、公職選挙法でどう対応していくのかという内容でした。前の講演の「あんの」氏に対し「やすの」ですとのことで、紛らわしくてすみませんと笑いを誘っていました。
午後は、神戸大学大学院法学研究科の砂原庸介教授が、自治体の領域と都市圏のズレと解決法について、石川県副知事の浅野大介氏が、高齢社会における災害復旧について、能登半島地震と奥能登豪雨をケースに講演しました。しっかりと振り返って今後に生かしていきたいと思います。

また、この研修とは別ですが、前日の5月14日には地方創生ベンチャーサミット2025に参加しました。実は開催前日に存在を知ったイベントだったのですが、内容の濃いイベントだったので、思い切って参加してよかったです。
冒頭の石破首相の基調講演には間に合わず、セッション2から参戦。このセッションのモデレーターを務めた佐藤大吾さんは、大吾さんがドットジェイピーを、私がI-CASを立ち上げ、大げさに言えば日本の議員インターンシップの歴史を作ってきた「同志」です(若干おこがましいですが、先方が同志と言っていたのでそう言わせてもらいます)。

そして、かつてその議員インターンに参加した経験のある、下鶴隆央さんは鹿児島市長として登壇。公務員は人件費をゼロ換算する癖がある、何かを買ったり、導入したりするときに、それで削減される時間は?という発想が必要だという話は全くその通りです。

同じセッションに登壇した熊本市長は、市長就任時に引き継ぎのために大量の紙のファイルが出てきて驚いたという話、レクチャーのために市長室の前に行列するのをやめさせたという話を、つくば市長は、「世界のあしたが見えるまち」を掲げ、インターネット投票などに取り組んでいるという話をしていました。西東京市でもあてはまる話かもしれません。参考にしていきたいと思います。